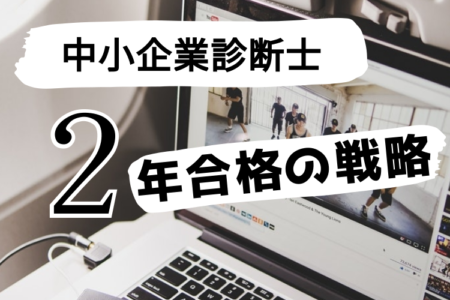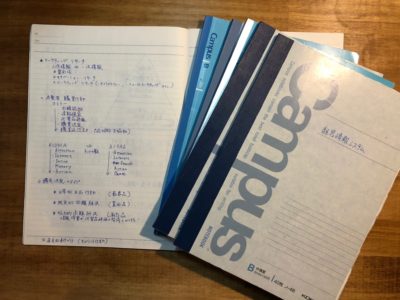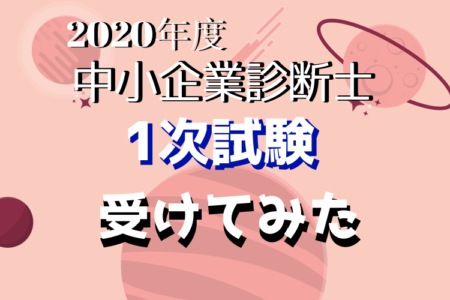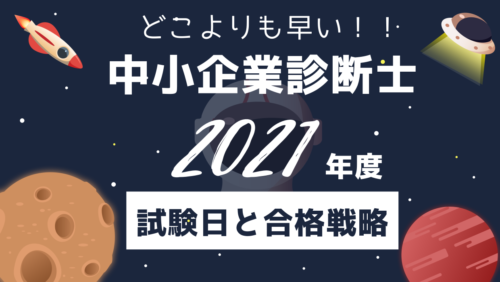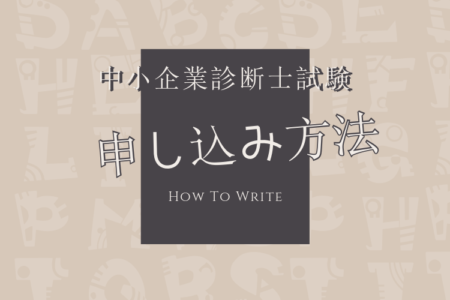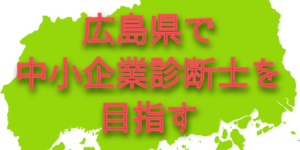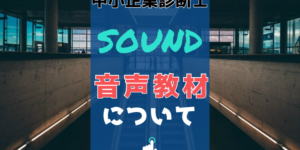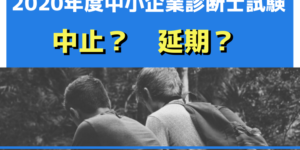中小企業診断士試験は一般に難関資格と言われています。
この『難関資格』という言葉から、高偏差値の難関大学卒業者じゃないと合格できないのではないか?という印象を受ける方は多いと思います。
例えば、中小企業診断士試験の合格者は東大・京大の国立上位大学や早稲田慶応などの超難関私大卒で固められており、低偏差値大学や高卒の自分では『そもそもチャンスがないのではないか』と思っていませんか?
しかし、実際は中小企業診断士試験に低偏差値といわれる大卒でも合格している方もいます。
今回は、中小企業診断士試験に一発合格の筆者が、偏差値が低いとお悩みの方が合格するための熱い戦略をご提案していきます。
Contents
中小企業診断士試験合格者の偏差値は?
| 申込者 | 試験合格者数 | 合格率 | |
| 経営コンサルタント自営業 | 263 | 57 | 21.7% |
| 税理士・公認会計士等自営業 | 543 | 128 | 23.6% |
| 上記以外の自営業 | 519 | 105 | 20.2% |
| 経営コンサルタント事業所等勤務 | 627 | 112 | 17.9% |
| 民間企業勤務 | 12,745 | 2,778 | 21.8% |
| 政府系金融機関勤務 | 352 | 86 | 24.4% |
| 政府系以外の金融機関勤務 | 1,948 | 469 | 24.1% |
| 中小企業支援機関 | 581 | 89 | 15.3% |
| 独立行政法人・公益法人等勤務 | 273 | 62 | 22.7% |
| 公務員 | 707 | 170 | 24.0% |
| 研究・教育 | 119 | 20 | 16.8% |
| 学生 | 564 | 59 | 10.5% |
| その他(無色を含む) | 1,922 | 309 | 16.1% |
| 合 計 | 21,163 | 4,444 | 21.0% |
偏差値が低い人は『中小企業診断士』に向いていないのか
偏差値を気にする人が中小企業診断士挑戦前にすべきこと
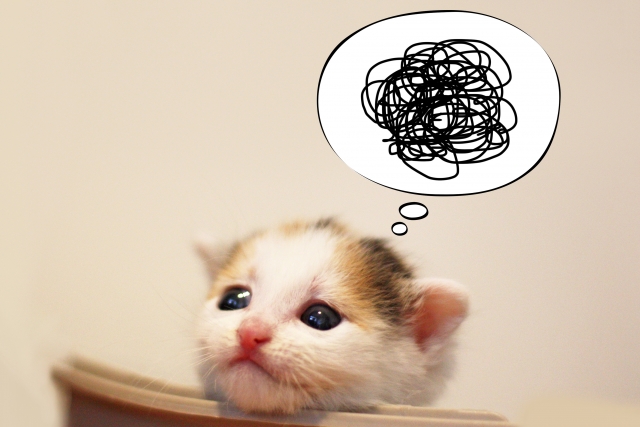
偏差値以外で試験難易度を知る唯一の方法
その方法とは過去問を実際に解いてみることです。
実際に過去問にぶつかってみて、体感としてこの試験の難易度を測るのです。
ありきたりだなあ、と思う人も多いかと思います。
しかし、判断方法は得点ではありません。
答案を採点した時に、『いずれこの問題を解けるようになりたい』もしくは、『これらの知識を身につけている自分になりたい』と感じるかどうかで判断してください。
あなたが過去問の論点について、知識として習得したいと思えれば、きっと学習も前向きに取り組めるはずです。
前向きに取り組めれば、自然と学習時間もかけられますし、学習時間をかけられれば合格にどんどん近づいていきます。
良いサイクルが出来やすいという点で、難易度は相対的に低くなります。
逆にこんなん別に知らなくていいや、と思えばあまり向いてないかも知れません。
学習がつまらないと感じ、途中で辞めてしまうからです。
中小企業診断士の一次試験は、基本的に知識問題です。知っているか、知らないかの二択です。
なので、中小企業診断士に合格するかしないかは知識の広さが決定要因で、難易度とは知識レベルが合格水準に達するまでにどれくらいの時間がかかるか、なのです。
中小企業診断士は時間をかければ、必ず合格出来ます。それは、一年かも知れないですし五年かも知れません。
しかし、途中で諦めてしまう人が多いから難関資格になっているのです。
つまり、中小企業診断士試験の受験を通じて学ぶことを自分が楽しめるかどうか。
これを確認することが、自分の学歴や偏差値で難易度を測ろうとすることよりも、自分の合格可能性を正確に把握できる方法なのです。
低偏差値を気にする人が試験難易度を測る具体的方法

上述の通り、自分にとって難易度が高いかどうかを判断するためには過去問を実際に向き合うことが一番です。
しかし、初学者が過去問へ向き合うには、少しコツがいります。
なぜなら、中小企業診断士一次試験の特徴として、同じ科目でも年度によって合格率の異常に高い年、低い年があるからです。
詳しくはこちら:中小企業診断士一次試験科目別難易度ランキングを公開!!独自データで合格難易度を検証。
このような異常変動の年の問題は、あまり良問とは言えず、初学者が自分にとっての難易度を測るのに適していません。
あなたが試しに取り組んだ問題が、これらの異常変動の年のものだった場合、自分に合っているかの判断を誤る可能性が高くなってしまいます。
下記に良問と思われる年度の問題を、科目ごとに示しました。
良問の判別基準は、一次試験の平均合格率である20%付近の合格率であること、としています。
つまり、簡単すぎず難しすぎず、平均的な合格者が合格できる問題を選びました。
ここから選んで解けば、大きくハズしはしないと思います。
下記が良問一覧です。
リンクも貼ってありますので、WEB上で解いてもよいですし、印刷して解いてみてもよいでしょう。
解答欄はありませんが、そこまでこだわらず適当に問題数分のマスを作って、回答していけばよいでしょう。
| 科目名 | 良問年度 | 解答時間 | リンク |
| 企業経営理論 | 平成27年度 | 90分 | |
| 財務会計 | 平成28年度 | 60分 | 平成28年度財務会計 問題 平成28年度財務会計 解答 |
| 運営管理 | 平成27年度 | 90分 | 平成27年度運営管理 問題 平成27年度運営管理 解答 |
| 経営情報システム | 平成30年度 | 60分 | 平成30年度経営情報システム 問題 平成30年度経営情報システム 解答 |
| 経済学・経済政策 | 平成26年度 | 60分 | 平成26年度経済学経済政策 問題 平成26年度経済学経済政策 解答 |
| 経営法務 | 平成27年度 | 60分 | 平成27年度経営法務 問題 平成27年度経営法務 解答 |
※経営法務は直近5年で20%付近の合格率がなく、掲載年度でも合格率11%くらいです。
※中小企業経営・政策は年度によってテキストが変わるので、あまり解いても意味がないので掲載していません。
それでも偏差値が高い人が有利な理由
②目標を勝ち取った成功体験を持っていること
偏差値を覆すための学習方法とは?
それでは、このような差を埋めるためにはどうしたらよいでしょうか。
それは、単純かつ唯一の普遍的な方法です。
他人よりも勉強時間を多くとればよいのです。
人が一日2時間勉強しているなら、自分は4時間する。
これだけです。
要領よく学習して合格しよう!などと考えてはいけません。
なぜなら、学習の要領のよさこそが、高偏差値者の強みだからです。
泥臭く、毎日の勉強時間を積み重ねていく。
これが偏差値を逆転する方法なのです。
私は、一次試験だけに1,000時間の勉強時間をかけました。
中小企業診断士試験合格に必要な時間は1,000時間と言われていますが、実際にこれだけの時間をかけている人は少ないでしょう。
冒頭に、中小企業診断士試験受験者の職業別一覧を掲載しましたが、ここに掲載されている職業の中には超多忙で学習時間が十分にとれない職業も多くいます。
ここに逆転のためのチャンスがあります。
自分の学歴で合格できるか?を詳しく調べる時間があるなら、いますぐに一歩踏み出すことのほうがよほど合格に近づけます。
それと、一日4時間勉強することは意外と苦痛じゃありませんよ。
社会人になってしばらく経っていると苦労をすることに慣れているからです(笑)
仕事よりは楽だな~、って思えます(笑)
『チャレンジする』と決めた方は、とにかく一歩踏み出しましょう!
このサイトは中小企業診断士試験の教材選びに強みを持っています。
下記のページを参考に、まずはメインの教材から取り組み始めてください!
中小企業診断士独学の教材費に【30万円】も使ったからわかる最適最安教材パッケージをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?
今回は偏差値が低いことを気にしているあなたが、中小企業診断士試験の難易度の知り、合格をつかむ方法をご紹介いたしました。
みなさんの学びが合格につながることを祈っています!!